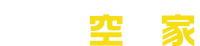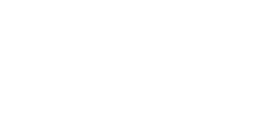土の中の病原菌や害虫を減らすためにビニールフィルムで覆われた畑。濃い緑の葉を四方八方に広げるターサイが整然と並び、畑の周囲は雑草が目立つ。「豊作で収穫作業が忙しくて、草刈りが追いつかないんですよ」。就農して4年目になる岡山県出身の秋山雄輔さん(29)は額の汗を拭いながら笑顔をみせた。
畑があるのは、東吾妻町との境に近い高崎市倉渕町権田。平屋建て住宅と周囲の畑を格安で譲り受け、妻の琴さん(28)と一緒にレタスやキャベツ、ターサイといった大型野菜を栽培している。収穫物の多くは所属する生産者団体「くらぶち草の会」を通じて販売する。昨年には化学物質に頼らない農地であることのお墨付き「有機JAS認証」を、草の会の支援を受けて取得した。
2人は東京大農学部の卒業生では珍しく就農を選び、2021年に移住した。「家族経営の農業を始めるのに、これほど環境がいいところはない」と雄輔さん。琴さんは神奈川県で生まれ育ち、田舎暮らしが憧れだったといい「地域の人が受け入れてくれて暮らしやすい。子育てをしながら畑仕事をする豊かな生活を満喫している」と満足そうだ。
高齢化と人口減少が進む倉渕町。3月末時点の人口は2836人とこの20年で4割減り、農地や水路などの保全、地域コミュニティーの維持といった中山間地に共通した課題を抱える地域もある。こうした中、真剣に農業に取り組む若者を全国から呼び込む草の会の存在感が増している。
有機農業の生産者団体の草分け的な存在で、1990年に新規就農者の受け入れを始めた。旧倉渕村が整備した滞在型の研修施設を活用し、毎年、複数の研修生を受け入れている。研修を終えて倉渕を離れる人もいるが、定住した人は40人を超える。
「最初は受け入れられている感じではなかったけど、徐々に『若い人が来てくれて助かる』と変わっていった」。1997年に権田に移住した、草の会2代目会長の和田裕之さん(60)はそう振り返る。地域の役職を進んで受けたり、道路愛護などの行事に積極的に参加したりする会員が多く、新規就農者が歓迎されるようになったという。
会員43人のうち26人が移住組で、住居や農地を確保しやすい権田(6、8区)や川浦(7区)で暮らす人が多い。263人と行政区別で人口が最も少ない8区は、和田さんの妻、佳子さん(58)が区長代理として自治会活動を主導し、15人いる消防団員のうち13人が草の会の関係者だ。川浦で400年の歴史がある獅子舞の保存会でも3人の会員が活躍している。
8区の消防団長を2期4年務めた鈴木康弘さん(58)は「農業をしたくてこの地にやってきて、先人が開拓した畑や生活用水を使わせてもらっている。恩返しをしたいし、中山間地で家族経営の農業を続けるには地域の活性化を考えないといけない」と話す。
元倉渕小校長で8区区長の小池政一さん(65)は「新規就農者は前向きな人が多く、地域の行事にも積極的。力を借りないと、地域が成り立たなくなる」と将来を展望する。
【メモ】移住先として存在感
新幹線駅があり東京へのアクセスが良い高崎市。テレワークが普及する中、移住先として全国でも目立つ存在となっている。
東京圏から地方に世帯で移住すると最大100万円(単身は最大60万円)を支給する国の「移住支援金制度」の支給実績は、2023年度に98件と全国の市町村で最も多かった。
倉渕、榛名、吉井の3地域に移住した人に、住宅ローンの利子を5年間、全額補助する独自の制度もある。人口減をいかに緩やかにするかは自治体共通の課題で、市も厳しい財政状況の中、本年度は移住支援金制度の負担に1億円、利子補給には8000万円の支出を見込んでいる。