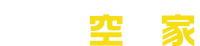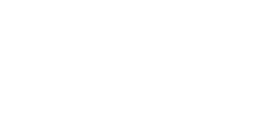2023年の県内全住宅96万7400戸のうち、空き家は16万1300戸で、住宅全体に占める割合が16・7%に上ることが11日までに、群馬経済研究所の調査で分かった。空き家の区分別で賃貸や売却、別荘など、明確な用途のない「その他空き家」(7万3100戸)の増加が顕著で、空き家全体の45・3%を占める。その他空き家は木造一戸建てが多く、同研究所は「木造は時間の経過とともに劣化が進む。高齢化でさらに空き家の増加が見込まれる」と警鐘を鳴らす。
5年に一度実施する総務省の「23年住宅・土地統計調査」に基づき、同研究所が初めて調査した。その他空き家率は県内全住宅の7・6%を占め、関東1都6県の中では最も高かった。空き家のうち、その他空き家に次いで多いのが賃貸用で6万8500戸、別荘などの二次的住宅が1万6千戸、売却用が3700戸と続く。
その他空き家は、03年が全住宅の4・8%に当たる3万8400戸。20年後の23年は、03年と比べて1・9倍の戸数となった。
数値が公表されている人口1万5千人以上の県内18市町のうち、その他空き家率が最も高いのがみなかみ町の20・8%。次いで中之条町の16・2%、安中市の14・2%と続き、中山間地域での比率が高かった。戸数では、高崎市が最も多い1万3210戸、前橋市が8940戸、桐生市が6300戸と続いた。
その他空き家のうち、「木造」「一戸建て」がともに80%を超えた。屋根や壁、柱などの腐朽や破損はその他空き家の24・8%の1万8100戸に上った。
居住者がいる住宅80万1900戸のうち、一戸建て住宅で65歳以上のみの世帯は23・2%の18万6千戸。そのうち、75歳以上の1人暮らしが5万2700戸で30%に迫る。
群馬経済研究所の高橋真澄主任研究員(61)は「防災や防犯、住環境保全の観点などからも放置できない課題。地域住民と自治体が一体で空き家が生じにくい街づくりを進めることが、問題の解消につながるかもしれない」と提案する。