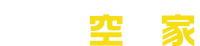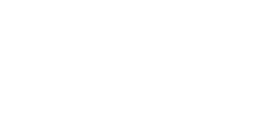高崎市請地町で3月28日に住宅など計12棟を焼いた火災で、火の粉が風で遠くに運ばれる「飛び火」で被害が広がったとみられることが2日までに、同市等広域消防局などへの取材で分かった。飛び火は、2016年に新潟県糸魚川市で約150棟が焼損した大規模火災の原因にもなった。専門家は「1センチに満たない小さな火の粉でも延焼する。住宅密集地では火元に挟まれる恐れもあるため、風向きを考えて避難経路を確保してほしい」としている。
28日の火災では火元とみられる一帯から、南にある県道高崎駒形線を挟み約50~70メートル離れた住宅2棟も焼損した。消防や県警によると、飛び火による被害とみられる。複数の住民によると、この日は北から強風が吹き付けていたという。
2棟の近くに住む女性(70代)は「火の粉がどう飛んで来るか分からなかったので怖かった。周りに空き家もあり、みんな自宅に水をまいて延焼を防いでいた」と振り返った。
飛び火は、これまでも大規模な火災の一因となってきた。国立研究開発法人「建築研究所」(茨城県つくば市)の水上点睛(てんせい)主任研究員(44)によると、糸魚川市の火災では150メートル先に飛び火した例があり、消火対象が15カ所に分かれたことで「鎮火を難しくさせた」と説明する。
火種が屋根瓦の隙間に入り込んで延焼につながるため、予防には屋根のメンテナンスが有効だという。2001年に施工ガイドラインが作られる以前の瓦屋根は、耐震性が弱い場合もある。水上さんは「特に古い瓦は注意が必要。ずれていたり隙間があったりする場合には、修繕を検討してほしい」と呼びかけている。